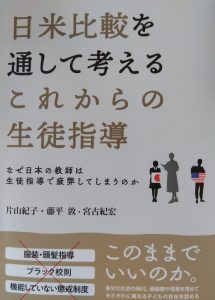医療の世界を社会学する
中川輝彦・黒田浩一郎 編著『よくわかる医療社会学』
(ミネルヴァ書房、2010年)

これまで、山本太郎さんの『感染症と文明』や立川(たつかわ)昭二(しょうじ)さんの『病気の社会史』など健康や医療について歴史的に考察した本を読んできましたが、今回は社会学の視点から現代医療と人々との関わりについて勉強してみたいと思い、医療社会学の入門書である本書を読んでみました。
本書は医療社会学を専門とする研究者15人が分担執筆しています。入門書ということで、この分野の知識があまりない読者にも分かりやすく解説されています。
「病人役割」という理論
本書を読んで勉強になったことの1つはタルコット・パーソンズという社会学者が論じた「病人役割(sick role)」についての議論です。パーソンズは「病気になる」ということは「病人という社会的な地位につく」ことであると考え、その地位についた人は「病人役割」を期待されるのだと考えました。「病人役割」の特徴は、①通常の義務を免除される、②病気の状態にあることに対する責任を問われない、③できるだけ早く病気の状態から回復する努力をするように期待される、④病院に行き医師も援助を求めることを期待される、というものです。また、こうした「病人役割」を期待する社会は、一定の健康な人々がいるということが基本前提になっており、社会の「ガス抜き」として「病人役割」が機能しているという議論をパーソンズは展開しました(7ページ)。
このパーソンズの「病人役割」論は高く評価され、その後の研究者によって批判や修正を受けながらも医療社会学の「古典」とされているそうです(8ページ)。パーソンズの「病人役割」論には、たとえば、②について「生活習慣病」の場合など病気になった責任を問われる傾向があることや、④について医者の指示通りに薬を飲むことを放棄したり、近代医療とは別の治療法(「相補・代替医療」など)を選択したりする患者の動向があるなどの批判や疑問が提示されていますが(9ページ)、「病人役割」というパーソンズの着眼は重要だと思いました。
「健康至上主義」とは?
本書を読んで勉強になった2つ目は「健康至上主義」という用語についてです。英語では“helthism”というそうですが、健康を最重要の目的とする傾向全般を指す言葉で、健康に関する本や雑誌の売り上げが伸び、健康食品や健康機器などの産業の規模が大きくなってきたというのが、1980年代頃からのアメリカや日本で起こった現象で、医療社会学では1990年代前半から、この現象を批判的に論じるようになっていったようです(45ページ)。健康は幸福になるための手段とは考えず、それ自体を目的とするのがよいのかどうかについては私も疑問があります。こうした動向の背景にあったもの、あるいは、それを批判的にみる有識者たちの背景事情なども今後の研究上の課題にあがっているようです。
平均から偏っていること
本書を読んで勉強になったことの3つ目は「監視医療(Surveillance Medicine)」についてです。健康な人も病気の人も含むすべての人々を対象とし、統計データを基礎にして病気になるリスクを割り出し、予防や健康増進を目指す医療モデルです。この医療モデルは特に20世紀に入って盛んになってきました(77ページ)。この「監視医療」という医療モデルの特徴について研究したのはイギリスの社会学者D. アームストロングです。アームストロングは、この「監視医療」では、健康と病気は明確に区別されるというわけではなく、平均から偏(かたよ)っている、つまり「異常」だということが病気の特徴とされるようになっていると指摘しました。学校などで行われる集団検診などの「検査」が、この「監視医療」の最前線だというアームストロングの指摘が紹介されていて、とても勉強になりました。
本書では、他にも近代医療に対する人々の不満を反映して、たとえば、国家免許をもたない者による治療法に頼る人々の動向なども触れられていました(159ページ)。日本でも西洋医学が普及する以前の漢方薬や漢方医療などがあります。これらは非近代医療、民間医療、代替補完医療、多元的医療システムなどの用語で医療社会学の研究テーマになってきいることが分かりました。本書は医療社会学の幅広いテーマが初学者にも分かりやすく解説された入門書ですので、現代の医療や健康をめぐる問題に関心のある方に是非おススメします。

![よくわかる医療社会学 (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ) [ 中川輝彦 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8211/9784623058211.jpg?_ex=128x128)