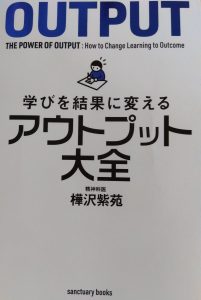人間と家畜の長くて深い関係
谷泰 著『牧夫の誕生 ―― 羊・山羊の家畜化の開始とその展開』
(岩波書店、2010年)
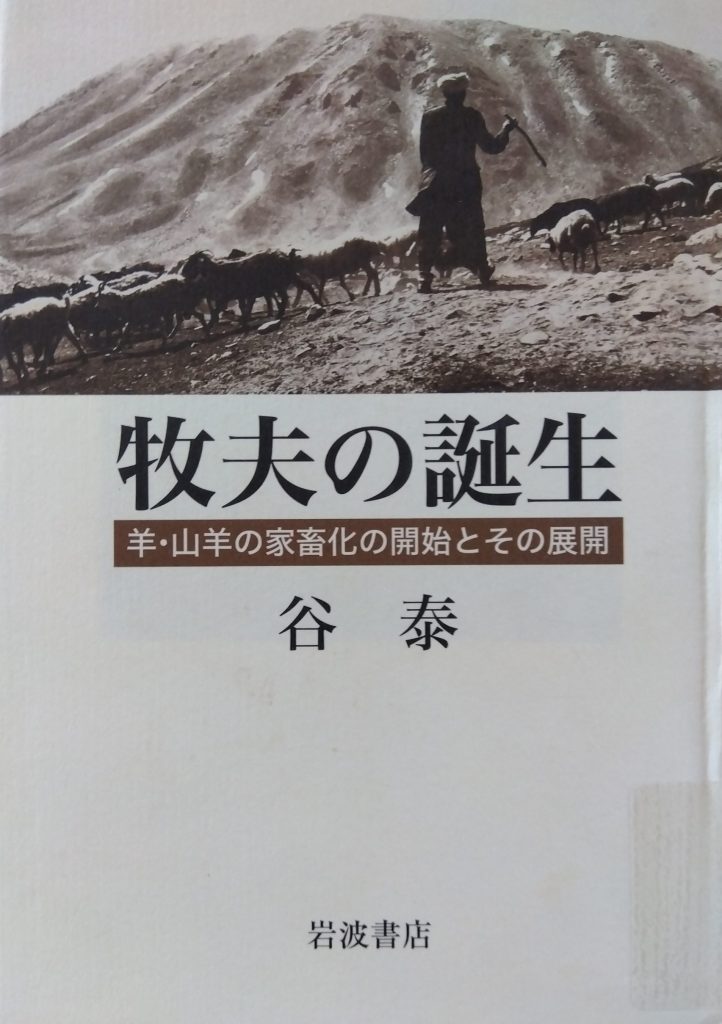
昭和の時代、『アルプスの少女ハイジ』というアニメがテレビ放送されていて(※宮﨑駿さん、高畑勲さんが製作に携わっていました)、主人公ハイジの友だちのペーターという山羊(やぎ)飼いの男の子がいました。スイスの山々が主な舞台で、ペーターは山羊の群れを草場に連れて行って草を食べさせ、夕方には山のふもとの小屋に連れて帰っていました。山羊飼いというのは当時の現実の私の生活からは馴染みのない仕事で、外国には不思議な仕事があるものだと思っていましたが、動物を家畜にするということを人間はいつ頃からどのように行うようになったのだろうという疑問をもつようになりました。その疑問に迫れそうな本として本書を見つけ読んでみました。
カトリック文化と牧畜文化
本書の著者、谷泰さんは西洋史を専門とする研究者です。以前、谷さんの『カトリックの文化誌 ――神・人間・自然をめぐって』という本を読みましたが、谷さんは西洋史のほかに、もうひとつの専門として文化人類学を研究されています。谷さんはカトリック文化に強い関心をもっていますが、カトリックの聖職者(司祭)の仕事の内容を表す言葉として〈パストゥール〉とか〈シェパァード〉という言葉があり、これは日本語に訳すと「羊飼い」です。キリスト教の聖職者が信徒たちを精神的に導くことが、しばしば、羊の群れを導き管理することと重ね合わされることに谷さんは注目しています(7ページ)。このような聖職者と羊飼いのイメージの重なりは西洋だけでなく、中国でも地方長官のことを〈牧民官〉と呼ぶことがありました。谷さんはカトリック文化の研究を深めるために、牧畜文化の研究に入っていき、牧畜文化についての研究の蓄積が多い文化人類学をもうひとつの専門にするようになったのだと思います。
動物の群れを追い込んで?
本書の内容は、私にとって今までほとんど知らないことばかりで、新たな発見が多くありました。人間が動物を家畜にする文化についての研究は20世紀後半になってようやく本格的に行われるようになったようで、未だ確定的な学説がなく、仮説を検証している段階だということが、まず大きな発見でした。そして、現時点での2つの有力な仮説があるそうです。1つは「追い込み猟仮説」です。紀元前1万年前後の新石器時代、人類最初の農耕が始まった西アジアで麦の栽培が広がった場所で、家畜文化の開始の証拠が多くみられます。その証拠のなかに、人間が動物の群れを追い込んで猟をしていたと推定される石造の囲い、網縄、弓矢などがあります(57ページ)。出土する骨から考えて、この追い込み猟の主な獲物はウシ科の哺乳類のガゼルだったと推定されていますが、人間はまず、この追い込み猟によって動物の行動特性についての知識を得て、猟の効率を上げていったと考えられます。そして、多くの獲物を生け捕りにすることができた場合、それらをすぐに殺すのではなく、しばらくは柵(さく)の中に保留して順次消費するということが行われるようになります。しかし、ガゼルは個体どうしが一定の距離をとる習性があることから密集居住には向かない動物で、ガゼルが家畜になっていくということにならなかった。その代わりに、羊や山羊は密集居住が可能で、しかも人間との親近性をつくりやすかったことから羊や山羊の家畜化が進行していった。これが家畜文化に関する「追い込み猟仮説」の概要です。
柵の中で次世代が生まれ育つ
もう1つの仮説は「群れの人付け仮説」で、羊や山羊などの動物の群れに対して人間が接近を繰り返し、徐々に親密な関係性を築いていったというものです。私は「追い込み猟仮説」のほうに現実味を感じますが、本当のところはどうだったのか判断はできません。谷さんはこの2つの仮説は両立可能だと述べています(72ページ)。
さて、家畜文化の開始には次のステップがあります。それは、農耕を開始し定住を始めた人間の生活圏の柵の中に羊や山羊を住まわせることが可能になった。その次のステップとして、人間が羊や山羊に豊富な草を与えることで、若い個体が生まれ、成長し、そこをホームグラウンドとする群れが育つようになるという段階があります。この群れは、そこで生まれ育ち、そこをホームグラウンドとしているので、そう簡単には逃げなくなります。このステップに入ることで家畜文化は本格的に始まると谷さんは解説しています(74ページ)。この解説は本当に分かりやすくて「なるほど」と思いました。
オスの間引き戦略、搾乳技法
こうして開始された家畜文化ですが、その後に開発されたいくつかの技法が本書に紹介されており、こちらも勉強になりました。たとえば、雄の間引き戦略という技法です。これは、子どもを生む雌や若い個体を残して、雄を優先的に消費することで群れの再生産を円滑に行うという戦略です。与える草の量と、採れる肉の量とを計算する経済効率の考え方も、人間は早くから気付いて取り入れていったと推定されるので、なんだか気が重くなりました。
それから授乳・哺乳に対する人間の介助の技法が開発され、これが搾乳(さくにゅう)につながっていくことも分かりました。出産した羊や山羊の雌は基本的に実子に乳を飲ませようとし、実子以外には授乳を拒否しようとする習性がありますが、実子を近づけたり、実子の匂いをかかせたりして授乳を促して、実子以外にも授乳させることが可能なことを人間は発見しました。これを「乳母(うば)付(づ)け技法」と呼ぶそうです。人間の世界での乳母については中田元子さんの『乳母の文化史』などを読んできましたが、動物の世界に乳母にまつわる技法があることを初めて知りました。
人間の生活にとって家畜は肉、ミルク、チーズ、バター、ヨーグルトなど欠かせないものになっていますが、その歴史がとても古く、その進化の過程でいろいろな技法が開発されてきたことが本書を読んで分かりました。これがカトリックの聖職者や中国の〈牧民官〉のイメージのもとになっていることも、とても興味深いと思いました。これからも家畜文化については勉強していきたいと思います。