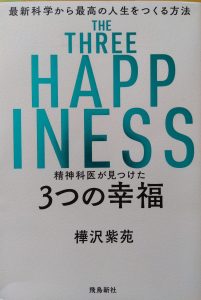少子化解決は「生活期待水準」がカギ!?
赤川学 著『これが答えだ! 少子化問題』
(筑摩書房、2017年)
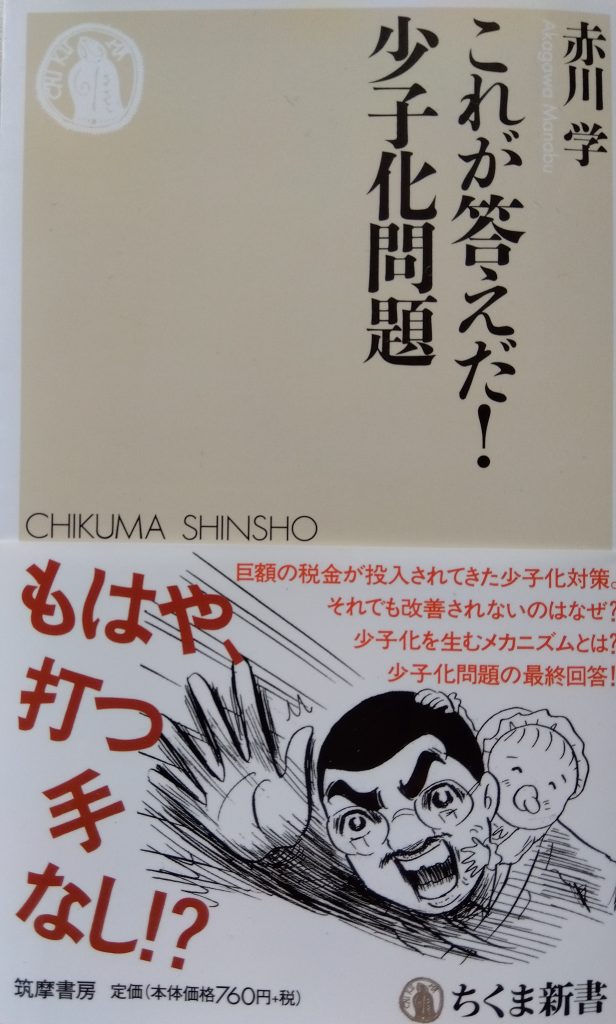
赤川学さんの本は以前に『少子化問題の社会学』(弘文堂、2018年)を読んだことがありましたが、本書は『少子化問題の社会学』の1年前に出版された本です。少子化という同じテーマの本を読むことで知識を増やし、掘り下げることを期待して本書を読んでみました。
本書の著者、赤川学さんは社会学を専門とする研究者です。本書が書かれた時期は、2014年に安倍内閣に「まち・ひと・しごと創生本部」が設置され、地方創生担当大臣が任命されるなど、少子化対策と地方活性化策が組み合わせられ、「2025年までに希望出生率1.8」が政策の目標として掲げられた時期です。「希望出生率」とは「結婚して子どもを産みたいという人の希望が叶えられた場合の出生率」という意味です。
「希望出生率1.8」は達成できそうにない
出生率の目標設定がなされたのは戦後初のことです(10ページ)。赤川さんは「希望出生率1.8」という目標値は、日本のように高齢化率の高い国では、女性が生涯に産む子ども数の平均値としてほぼ最大で、国が若い世代の男女に「結婚して、子どもを2人以上産んでください」と求めていることに等しいので、これは実のところ「国家規模のセクハラ」ではないかと述べています(11ページ)。「なるほど」と思いました。少子化対策というのは、子どもを産む数が増えるように国民を誘導する政策のことなのではないかと気付きました。
結婚・出産を政策で左右できるか?
赤川さんは「日本の少子化対策を講じる論者には、政策によって結婚や出生行動を左右できるという思い込みが強すぎる」と指摘しています(183ページ)。具体的には、ここ20年ほどの日本の少子化対策は、出産や子育てによって仕事を中断したり所得が減少したりすることを、子育て支援や働き方改革によって緩和・軽減することによって、結婚や出産にインセンティブ(刺激、誘引)を与えることを目指してきた。この背後に、得になると思えば出産し、損になると思えば出産しないという合理的な行為者、いわば「経済学的人間像」が想定されていると赤川さんは指摘しています(183ページ)。しかし、人間はそれほど単純ではなく、この「経済学的人間像」には限界があるというのが赤川さんの考えです。実際に2021年6月に発表された日本の合計特殊出生率は1.34で、5年連続で下降しています。「2025年までに希望出生率1.8」という少子化対策の目標は達成できなさそうです。
少子化対策というより社会福祉として
人口データに関して本書から得られる知見は豊富です。たとえば、①1人あたりGDP(国内総生産)の高い豊かな国は、出生率が低い。②日本やアジアの大都市圏は、農村部や村落部に比べて出生率が低い。③世帯収入の低い女性の子ども数は多い(136ページ)。これらに関する報道やネット上の情報には混乱しているように思いますが、本書ではきちんと検証されて、これらの知見を導き出されています。
本書では、待機児童の解消や子育てコストの軽減などは少子化対策というより社会福祉として重要だとされています(184ページ)。そして、カギとなるのは「生活水準」と「生活期待水準」との関係です。中流や上流生活への「上昇」を望む人々は、現状の「生活水準」より高い「生活期待水準」をもっているのですが、こういうマインドにある人々は子どもを多くほしがらないので少子化が進行すると赤川さんは述べています(186ページ)。これが「経済学的人間像」が想定する損得勘定より深層にあることを強調するのが本書の特徴だと思いました。現時点の私はこの真偽を確かめる力はありません。
生活水準が実際に高まれば
赤川さんの考えでは、少子化対策によって打ち出される政策項目が、よりよい出産、よりよい育児に対する期待を高める、つまり「生活期待水準」を高めるだけに終わっていることが問題です。そして、「生活期待水準」を高めるのではなく実際に「生活水準」を高める社会福祉的な政策こそ少子化克服のカギだと赤川さんは述べています(185ページ)。政府が打ち出してきた少子化対策とは別の角度から眺(なが)める社会学の知見として重要だと思いました。
コロナ禍ということもあり少子化対策はさらに困難になっているようです。今後、どのような対策が打ち出されるのかには注目する必要がありますが、対策の中身を検討する際に、本書から得られた知見を活用していきたいと思います。

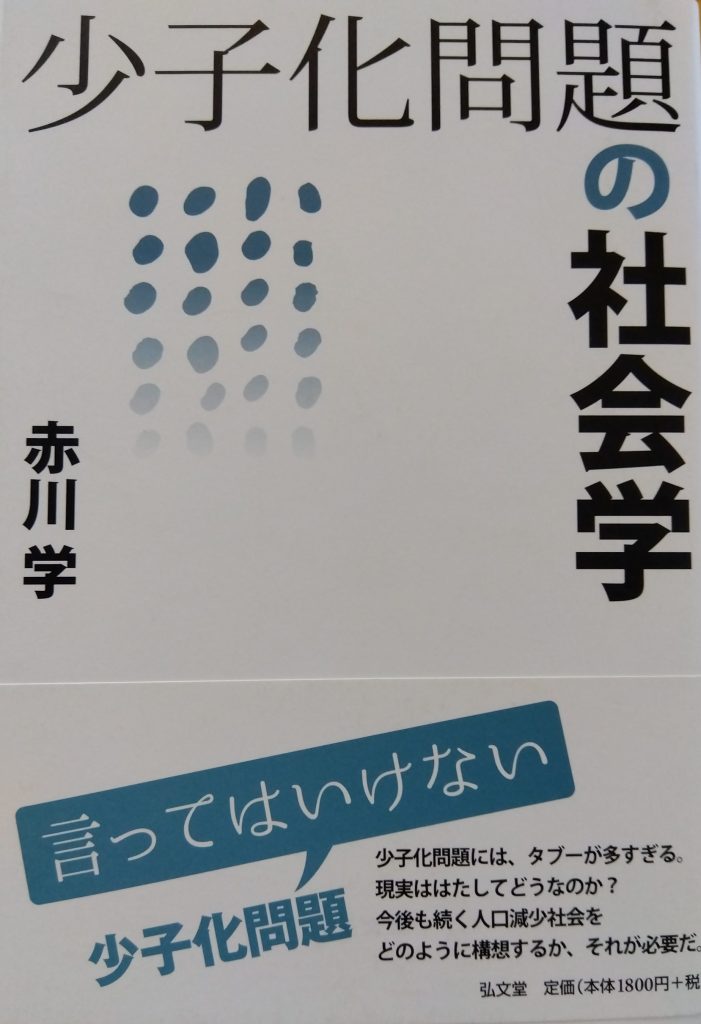
![これが答えだ! 少子化問題 (ちくま新書) [ 赤川 学 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9368/9784480069368_1_10.jpg?_ex=128x128)