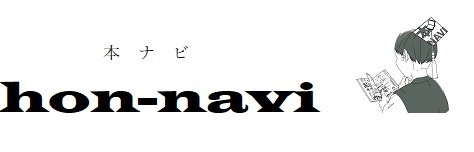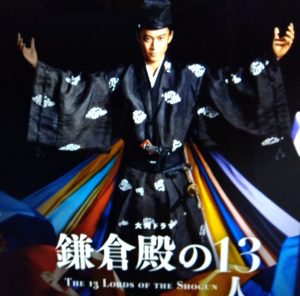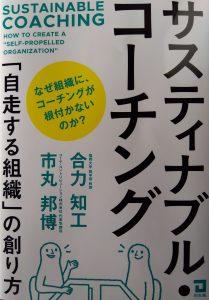(コーチング)「気づき」を与える禅、心理学、脳科学
合力知工・市丸邦博 著『サスティナブル・コーチング』
(同友館、2021年)
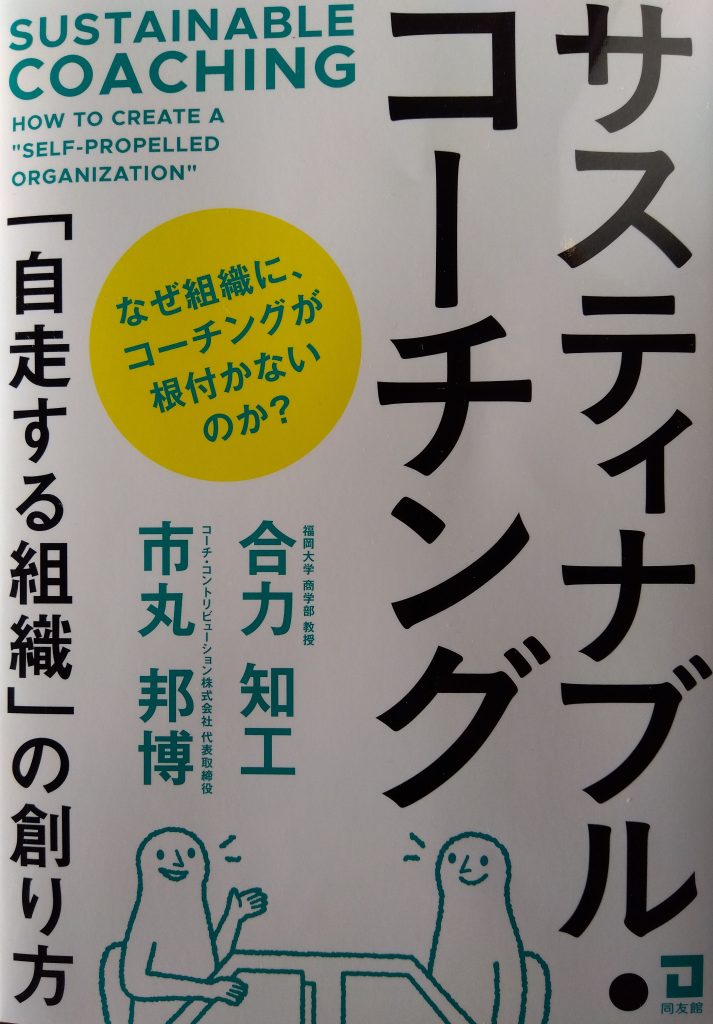
スポーツ選手や組織の部下を育てる方法としてコーチングというものがあるということがよく言われていると思います。しかし、その中身はどのようなものなのか、具体的な方法を知るために本書を読んでみました。
私はコーチングの基本すら知らない状態で本書を読み始めましたので、序章のところでもいくつか勉強になったと思える箇所がありました。
その1つは、コーチングは「気づき」を与えるものだということです(ⅳページ)。何かを教えるというティーチングとは根本的に違います。
コーチングの基本の流れは①コーチがクライアントの話を聴く、②コーチが承認する、③コーチが質問する、④クライアントとコーチが気づく、というものです。④に「気づく」があります。この「気づき」を得るために聴く、承認する、質問する、ということを繰り返すのがコーチングの基本なのだと分かりました。
もう1つ分かったのは、コーチングと相性がいい学問として、「禅的思考」「ポジティブ心理学」「脳科学」があるということです(ⅶページ)。コーチングをコーチや組織が継続的に行っていくためには、コーチングを支える考え方(パラダイム)をコーチが学ぶ必要があり、そのとき特に役立つのが「禅的思考」「ポジティブ心理学」「脳科学」の3つだと本書は提唱しています。
本書では、京セラやKDDIの創業者の稲盛和夫さんの『生き方』という著作が紹介され、稲盛さんの考え方の中に「禅的思考」が大きな影響を与えていたと述べられています(30ページ)。その中身を具体的に探っていきたいと思いました。