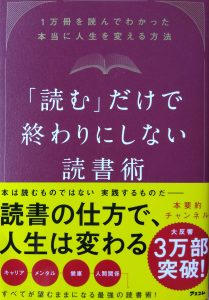「子ども」をどのような存在と考えるか?
元森絵里子/高橋靖幸/土屋敦/貞包英之 著『多様な子どもの近代――稼ぐ・貰われる・消費する年少者たち』
(青弓社、2021年)
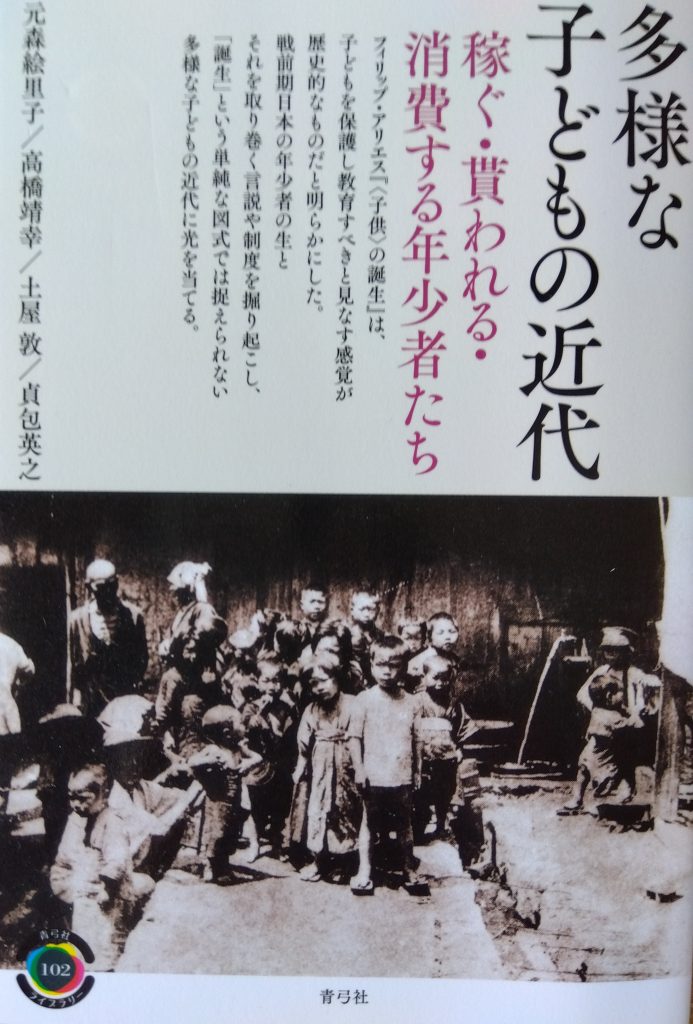
「子ども」という研究対象
以前、森田ゆりさんの『しつけと体罰』という本を読みました。森田さんは、日本とアメリカで児童虐待防止の活動を行ってきた人で、とても重要な社会活動をしておられる方だと感じました。また、2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられたことに関連して廣瀬健二さんの『少年法入門』という本も読み、少年の犯した事件や罪に対して保護・教育的な対応が取られているということも分かりました。子どもを大事に育て、虐待などから保護するという意識は時代や社会によって強弱や濃淡があるようです。今回は、その点を詳しく検討した本書『多様な子どもの近代――稼ぐ・貰われる・消費する年少者たち』を読んでみました。
本書の著者の元森絵里子さん、高橋靖幸さん、土屋敦さん、貞包英之さんの4人は社会学をベースとして子ども研究を行っている研究者です。4人は研究テーマの近さから研究交流を行い、今回一冊の本を執筆することとなりました。
児童労働が禁止されても
本書の著者4人に共通する問題感心は、フランスの歴史家フィリップ・アリエスが1960年に出版し、1980年に日本語にも翻訳された『〈子供〉の誕生』という本のインパクトをしっかりと受け止めつつも、「近代的子ども観」とひとくくりにされるような単純な歴史認識や子ども観を修正することにあります。つまり、「子ども」に関する感覚や制度は近代社会で「誕生」したもの(24ページ)で、その「近代的子ども観」が社会のすみずみに浸透していったというような素朴な理解では捉えきれないような子どもの生活実態や処遇のあり方を分析することが本書の著者たちの共通の課題です(33ページ)。ひとくちに「近代的子ども観」といっても、それは家庭での育児、保健衛生、少年審判、ソーシャルワーク、精神医療などが絡まり合った複合的なものであって、しかも、そこから逸脱していく現象もある。本書の題名にある「多様な子ども」とはそのように意味が込められています。
子ども観の多様性という点で言うと、児童労働を制限・禁止した工場法というものがあることは有名ですが、本書の第1章で触れられているように、子どもに曲芸をさせたり大道芸(サーカス)に雇ったりというのは、近代的な工場での児童労働のカテゴリーの外にあり、「芸なのか虐待なのか線引きが難しいもの」(70ページ)でした。そのため、明治末期の時点では、子どもが獅子舞を演じる「角兵衛獅子」のような一種の曲芸は禁止の対象とはならずに温存されたということです(71ページ)。この事例は本書を読んで最も印象に残りました。
欧米の児童虐待事例が参照される
次に勉強になったのは、子どもの保護を熱心に進めるグループが、児童虐待を社会問題として構築する方策として欧米諸国の事例を持ち出し、欧米のような活動を日本でも行なうことを正当化しようとしたという点です(92ページ)。また、動物虐待と児童虐待を比較して、子どもの保護活動を進める動きもあったということも考えさせられる事例でした。
里親委託が減少した1910年代
さらに興味深かったのは、戦前期に、親のいない孤児や捨てられた子ども、浮浪児などを収容していた東京市養育院という施設で、収容後の子育てを里親に委託する措置が減った時期があったことです。それは1910年半ば頃だったそうです(157ページ)。この現象についての分析では、それまで「母乳」でしか生存させることができなかった状況は、代替用のミルクなどで施設内でも生存させることが可能となり、施設から学校に通わせて教育を受けさせることが子どものためになるという考えが強まったためだと指摘されています。つまり、「里親委託による生存」よりも「施設から学校に通わせて教育を受けさせる」ということが優先されたということで、ここでは近代的な複数の「子ども観」が多層的に交錯・拮抗するなかで、特定の「子ども観」が優先されるということがあったということが説得的に論じられていると思いました。
このように、本書では「子ども観の多様性」というテーマが豊富な事例をもとに分析されており、これまで単純化されて理解されがちがった「近代的子ども観」という概念をより深く理解するのに有益な本だと思いました。ふだん、子どもと接する機会の多い保育士さんや教員、児童相談所などでお仕事をされている方に是非オススメしたい1冊です。

![多様な子どもの近代 稼ぐ・貰われる・消費する年少者たち (青弓社ライブラリー 102) [ 元森 絵里子 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4964/9784787234964_1_47.jpg?_ex=128x128)