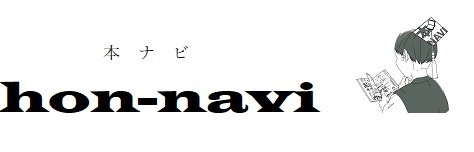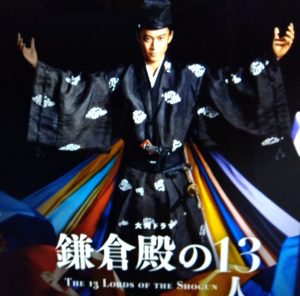高校「歴史」にもアクティブ・ラーニングの波:暗記科目から脱却できるか?
及川俊浩 編『アクティブ・ラーニング実践集 近代・現代』
(山川出版社、2021年)
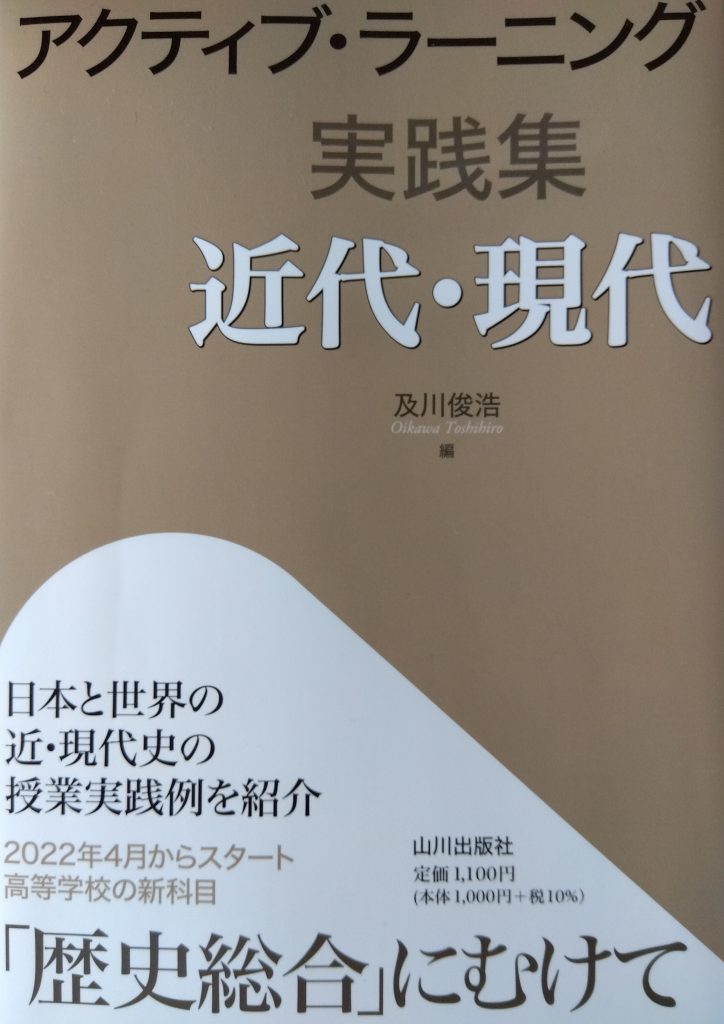
歴史は「暗記科目」という印象があります。暗記した知識の量が勝負という感じで授業はあまり楽しめませんでした。でも私はNHKの大河ドラマが好きで、小学校のときに放送していた「徳川家康」を観て楽しんでいました。最近でも明智光秀を主人公にした「麒麟が来る」もとても面白かったです。それからマンガの「三国志」も全60巻も興奮して読んでいました。
暗記の多さとは別として、歴史には登場人物の考え方や当時の風習、時代の変化などを想像する楽しさがあると思います。教育現場のアクティブ・ラーニングの波にのって学校の日本史・世界史の授業も楽しいものになる兆しはないのかと思い本書を読んでみました。
本書の編者は私立中高の教員の及川俊浩さんです。執筆者には、同じく中高の教員7人が加わっています。
本書を読んで私が特に勉強になったのは以下の4点です。
1. 2022年から高校の歴史科目が新設された
高校のカリキュラムには2022年から「歴史総合」「日本史探究」「世界史探究」が新設されました。科目名に「探究」がついていることが、従来の講義型の授業からアクティブ・ラーニングへの転換を示しているように思います。本書は、そのような高校の歴史科目の変化に教える側がしっかり準備できるように、教員向けに編集された本です。
2. 紙芝居を使うアクティブ・ラーニング
本書に「紙芝居プレゼンテーション法」、略してKP法というのが紹介されていました。これはA4サイズの紙に用語や重要概念を書いて、黒板やホワイトボードなどに貼りながら話をする手法です。前回の授業で習った用語などを紙に書いておき、それを黒板・ホワイトボードに貼って、生徒を指名して説明させるという授業法が紹介されていました(3ページ)。これは講義型の授業とは異なる方法で、アクティブ・ラーニング的だと思いました。
3. 資料を1枚足す
教科書を用いて授業をするのがオーソドックスな方法ですが、本書では「資料を1枚足す」という方法が紹介されていました(29ページ)。足すのは、当時の世相や人々の生活を表わすように写真です。教科書にも図や写真は掲載されていますが、それと関連しつつも掘り下げたり、違った角度から考察したりできるような素材となる写真を足すという工夫があると面白いと思いました。これは堀裕嗣さんの『道徳授業で「深い学び」を創る』という本でも紹介されていた方法です。歴史の授業でも同じ発想で工夫することができるのだなと感心しました。
4. アクティブ・ラーニングと受験指導は両立するか
このような議論が行なわれることが教育現場にはあるようです。本書の立場は「両立する」というものです(38ページ)。従来の講義型を「詰め込み」と特徴づけ、新しいアクティブ・ラーニングと対立的に考えるということは避け、両者を融合させるという立場のようです。これは齋藤孝さんの『新しい学力』でも主張されている考え方です。
本書では「生徒が歴史の知識を手足のように自由に使えるようになることを意識し、生徒の脳が常にアクティブな状態になるように意識して授業をおこなえば、おのずと成績も含めた結果はついてくる」と主張されています(38ページ)。
具体例としては次のようなものがあります。
①単元が終わるごとに、「この単元で登場した人物のなかで、この学校の校長先生になって欲しい/なって欲しくない人とその理由は」という問いを投げかける。
②今年起こった世界の出来事のなかで50年後100年後の世界史の教科書に載っている出来事はあるか、またその理由を話し合う。
私は、歴史の知識を活用して今の社会を考えることは大事だと思うので、このような具体例は面白そうだと思いました。
私の高校のときの世界史の授業は、穴埋め式の書き込みノートを用いて、先生が話をしながら、その穴埋めをしていくスタイルでした。穴埋めをするので手を使いますが、書かれている文章が「とっつきにくい」感じがして、分かりやすくはありませんでした。眠くなったときもあります。それと比べると最近の歴史の授業はアクティブ・ラーニング型を取り入れて、面白くなってきているのだなと感じました。