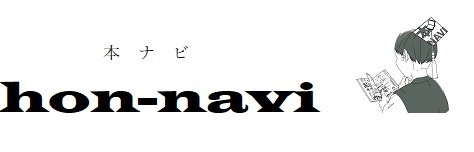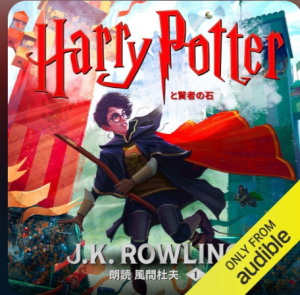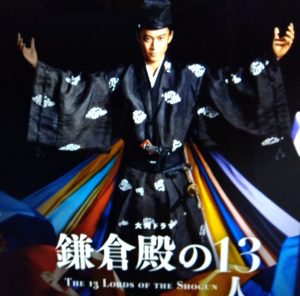日々のネタ集めを「深い学び」につなげる道徳授業のつくり方
堀裕嗣 著『道徳授業で「深い学び」を創る』
(明治図書、2019年)
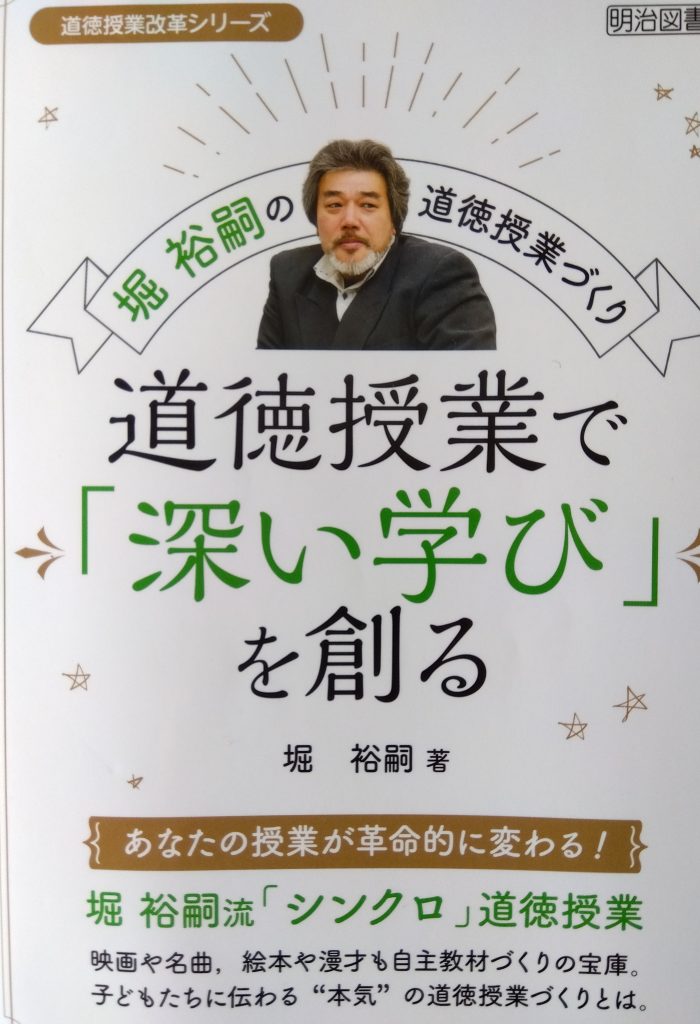
堀裕嗣さんは北海道の中学校で国語を専門として教鞭をとっておられる方で、以前、堀さんの『教師の仕事術』という本を拝読して、手帳を使ったスケジュールの大切さを学ばせていただきました。多忙だと言われる教員の世界にあって、堀さんは勤務時間内にほとんどの仕事を済ませて、ご自身の著書や教育雑誌などの原稿を執筆されています。今回は、そんな堀さんが道徳の授業づくりについて論じた本書を読んでみました。
本書が出版されたのは2019年ですが、この年から中学校で「道徳」が教科になり、教科書を使用して授業を行うことが教師の職務になりました。これはすでに小学校では2018年から始まっています。
堀さんが本書を刊行したのは、「道徳」の授業を本格的に開発して実施しなければならなくなった小中学校の教育現場において、どうせやるなら面白い授業を創っていこうという意志の現われだと思います。本書を読んで私が特に勉強になったのは以下の3点です。
1. 授業は〈後ろ〉からつくるのがコツ
堀さんは道徳授業に限らず、国語授業でも〈後ろ〉からつくっていくことを推奨しています(66ページ)。〈後ろ〉に、この回の授業の核心となる部分を配置しておき、それが活きる情報を冒頭から与えることを続けることで、生徒が深く考えることができる展開にする、というのが堀さんの授業づくりのポイントです。
逆に、おもしろい導入部分を思いついたとしても、それが授業の末尾まで展開していけるとは限らない。こういう経験を堀さんもしてきたようです。
そして、小説や漫画は結論を決めずに書き始めたものでも、よい作品になることがあるが、授業は違うと堀さんが述べています(65ページ)。この点は本当に面白いと思いました。
2. ネタ集めにこだわる
堀さんは『教師の仕事術』で、自分の思考を深めるのに役立ち、何かの原稿に引用できそうな文章を見つけたらパソコンの文書に書き起こして保存しておくと述べていました。道徳授業のネタ集めでも、それと同様のことを行なっているそうです(112ページ)。インターネット上の記事、画像、動画などを大容量ハードディスクに保存し、散逸させない。こうして集めたネタが授業づくりに活かされます。
堀さんは「純粋なオリジナリティは存在しない」と述べています(114ページ)。素材どうしの組み合わせによって、新しい視点が生まれたり、思考が促進されたり、ということがあるということだと思います。
3. 教科書と自主教材を組み合わせる
堀さんは、道徳授業を教科書だけを用いて行うことを「ソロ」と名付け、自主開発した教材と組み合わせることを教科書と自主教材との「コラボ」と名付けています(121ページ)。
「コラボ」の作り方にはバリエーションがあります。最初に教科書を読み、次にそれと内容的に関連する自主教材を読む。あるいは、教科書と自主教材を並べて比較しながら進める。こういう教材どうしの「コラボ」のさせ方を考えるのは楽しそうだなと思いました。
道徳は「A自分自身」「B人との関わり」「C集団や社会」「D生命や自然」という4つのカテゴリーについて学ぶことになっています(10ページ)。堀さんは、これらの項目を教える道徳授業は「居心地が悪い」と述べています。押しつけられる道徳は、結局は生徒の役に立たないと私は思います。生徒とともにAからDを考える授業が行なわれるといいなと感じます。