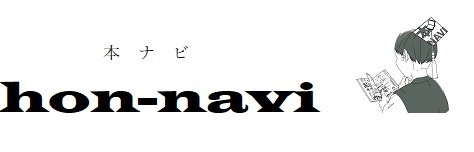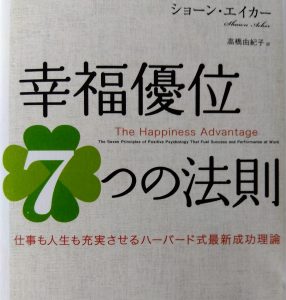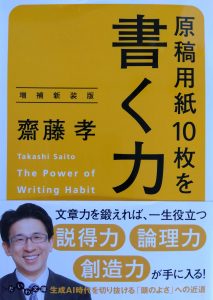角田光代『方舟を燃やす』:不三子が母親に言ってあげたかった言葉
角田光代 著『方舟を燃やす』
(新潮社、2024年)
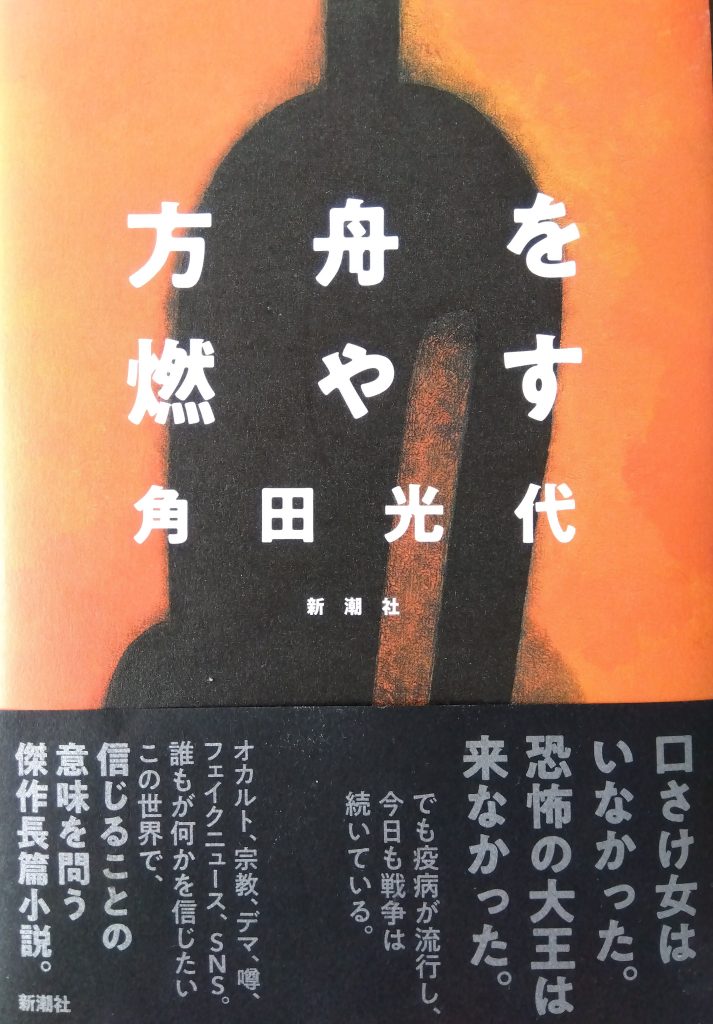
角田光代さんの最新小説『方舟を燃やす』を読みました。以前、角田さんの『対岸の彼女』を読んで、内面描写や人間関係の描き方が本当にリアルだと感じた作家さんです。
この小説の主人公は柳原飛馬と望月(旧姓、矢部)不三子の2人。年齢は不三子のほうが10歳以上、上です。2人が恋愛するとか、結婚するとかのストーリーではありません。住んでいる場所も全然離れていて、接点がありません。
この小説は、時代状況と2人の主人公の人生が重ね合わせられるかたちで、静かに進行していったように感じました。『対岸の彼女』のほうが、激しい展開があったように思いました。
不三子という女性は結婚した直後から添加物の多い食事を避ける自然食にのめり込んで行きます。そのきっかけは公民館で聞いた、自然食の指導者の話に感銘を受けたことです。自分と娘、息子には玄米食を貫きました。夫はそれに強く反発し、夫の食事は別のものを作ります。そして、娘、息子が学校に入学すると、学校に直談判し、給食を食べさせず、玄米中心の弁当をもたせます。さらには、予防接種の必要性に疑問をもち、自分の娘、息子には予防接種を受けさせませんでした。
そして、不三子の人生は、世間との折り合いがあまりうまくいかない人生として描かれていました。不三子の母親は戦時中に女学校で教師をしていて、国の方針にしたがって、「お国のため」に軍国少女を育てたことを終戦後ずっと悔いて、何もかもに無気力だったそうです。そして、不三子は、ある時期から娘の反抗を受け、娘は家を出ていって音信不通になってしまいました。
そんな不三子が高齢者となって、娘とうまくいかない自分を責めながら、自分の母親の気持ちを徐々に理解するようになったとき、次のように考え、母親に「言ってあげたい言葉」が浮かんできました。
「しかたがなかったじゃないか、何がただしいかなんて、みんな知らなかったんだから。神さまのような存在だって、知らなかったんだから。私たちのだれも、知るはずがないんだから。
いっさいのよろこびもたのしみも持たないよう、慎重にそれらを遠ざけて、後悔の奥底から一歩たりとも出ようとしなかった母に、今、不三子はそう言いたかった。その無気力と無関心を軽蔑し、忌み嫌った母に、そう言いたかった。言ったって、その暗い場所から出てこようとはしなかっただろうけれど、でも、言ってあげたかった。」
『方舟を燃やす』のなかで、この言葉がとてもいいと思いました。世間とあまりうまく折り合えない人生を送ってきた不三子だからこそ、たどり着いた思いがよく表れている言葉だと思うからです。
角田さんはいろいろな文学賞を受賞されていますし、小説の一部は高校の国語の教科書にも掲載されているようです。角田さんの他の本も読んでみたいと思いました。