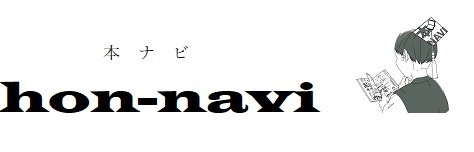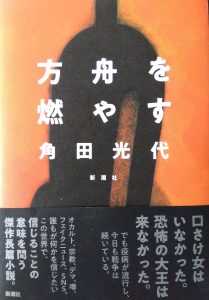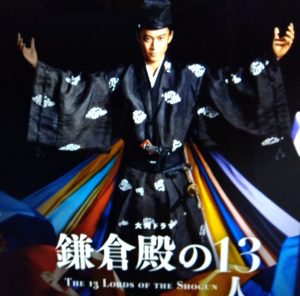信長の首を取れなかった「光秀の失敗」が、歴史を動かした
加来耕三 著『「本能寺の変」で光秀が犯した失敗』
(Audible、2015年)
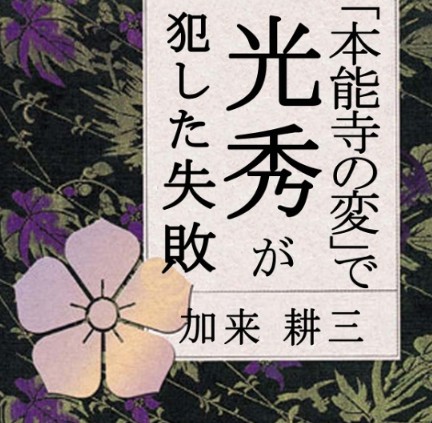
アマゾンのオーディオブックAudibleに「聴く歴史」というシリーズがあります。月額1500円のサブスク会員の場合は追加料金はかかりません。このシリーズから加来耕三「『本能寺の変』で光秀が犯した失敗」を聴いてみました。(所用時間1h02)
大河ドラマで人気があるのは戦国時代と幕末です。私も小学校のときから「徳川家康」などの戦国武将ものは大好きでした。明智光秀は主君である織田信長に謀反を起こしたことで「悪者」扱いされることが多かったように思います。しかし、2020年のNHK大河ドラマ『麒麟がくる』の主人公が明智光秀になったことでイメージが180度変わりました。光秀を演じた長谷川博己さんのカッコよさのせいもあったと思いますが、今の私にとっては光秀こそがヒーローで、信長が「悪者」という印象になってしまっています。
さて、このオーディオブック「『本能寺の変』で光秀が犯した失敗」では、光秀は有能な武将だったが、本能寺の変のとき、信長の首を取れなかったことが最大の失敗だったと指摘しています。光秀が本能寺に襲いかかったとき、信長は本能寺に火を放って、火のなかで自害しました。それで光秀は信長の首を取れなかった。
この失敗によって、「本当は信長はどこかに逃げのびて、今でも生きているのではないか」という思いが光秀にも、他の戦国武将たちにも湧き上がることになります。
そして、中国地方で毛利と戦っていた秀吉は、この「信長が死んだという確証はない」ということを利用して、各地にうわさを流しました。そうすることによって、光秀に味方する武将を少なくすることをねらい、実際にその情報作戦は成功しました。
ところで、「本能寺の変」はなぜ起こったのでしょうか? つまり、光秀はなぜ主君である信長を討つ謀反を起こしたのでしょうか?
この点は、歴史家の間でいろいろな検討がされており、諸説あります。このオーディオブックでは、当時の光秀の心中が推測され、信長の家臣として戦に明け暮れる日々に対する疲れが織田家の多くの家臣たちの間にあったと指摘されています。
実際に、信長の敵は中国地方の毛利の他にも、九州、関東、北陸、東北にも残っていました。「天下布武」を掲げる信長は、光秀や秀吉、柴田勝家のような有能な織田家の家臣団の武将を、まるで道具のように使う傾向がありました。著者の加来さんは、光秀よりも先に秀吉が信長に対する小さな裏切りをしたと指摘しています。北陸の上杉攻めをする柴田勝家の援軍をするように信長に命じられた秀吉は、柴田と揉め事を起こして離反したということがあったということです。この点を私は今まで聞いたことがあったかもしれませんが、ほとんど忘れておりました。
「本能寺の変」については本当にいろいろな説があります。諸説のなかには、織田信長が同盟を結んでいた徳川家康を討とうとして明智光秀に実行役をさせようとしたが、徳川家康と共謀した光秀が信長を討ったとする「逆ドッキリ説」まであります。このオーディオブックは、その説は採用していませんが、信長に長年仕えた佐久間信盛という武将を急に追放したこと、次第に傲慢になる信長の様子が述べられていて興味深かったです。また、比叡山延暦寺の焼き討ちについては『麒麟がくる』とは異なる解釈がされているようにも思いました。このオーディオブックを戦国時代ファンのかたに是非おすすめします。