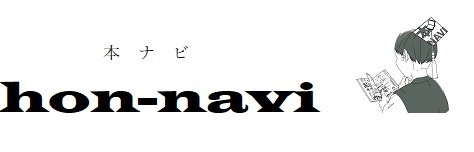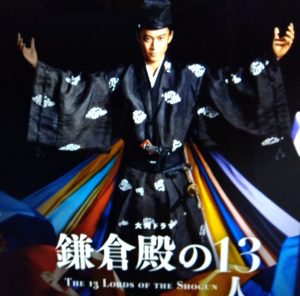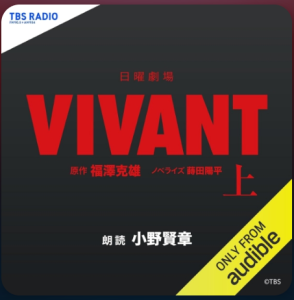(ワークライフバランス)会議の時間・資料・人数を半分にするという課題
小室淑恵 著『プレイングマネジャー「残業ゼロ」の仕事術』
(ダイヤモンド社、2018年)
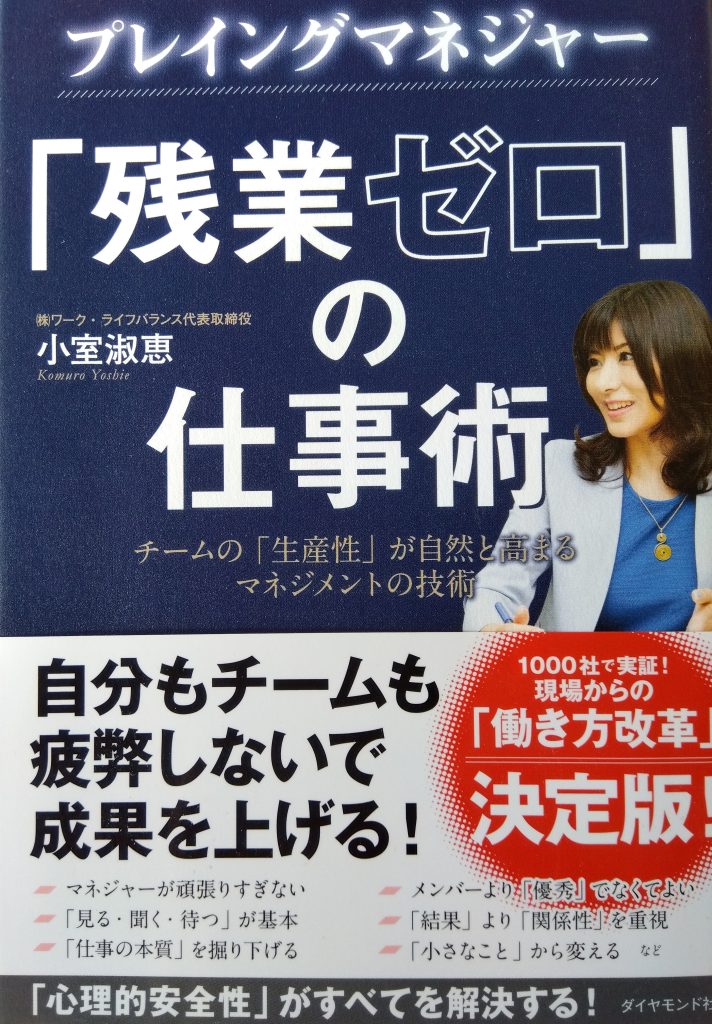
数年前「働き方改革」がとても話題になって、残業に対する罰則が厳しくなってきました。残業しないように、つまり定時で帰れるように効率よく仕事を進めることができれば家庭生活や余暇の生活も充実していくと思います。その具体的な方法を学ぶために本書を読んでみました。
本書の著者・小室淑恵さんは㈱ワーク・ライフバランスの代表取締役で、企業や官公庁の働き方改革の進め方を専門的にアドバイスされている方です。働き方改革に関する政府関係の委員も務められたそうです。
さて、本書で取り扱われている「プレイングマネジャー」というのが読む前はピンと来ていなかったのですが、本書の冒頭で「現場の仕事を担当しながら、チームのマネジメントもしなければならない」ような立場の人を指すということでした(ⅱページ)。これには企業の中間管理職もあてはまる場合もありそうです。また、看護師のなかの部門長だとか、教員の主任など、マネジメント専従でない立場の人はこの「プレイングマネジャー」ではないかと思い至りました。とても幅広く該当する人がいるなと思いました。
小室さんによると、「プレイングマネジャー」は会議の数が多いうえに、メンバーからの報連相、突発案件への対応などが求められ、さらに自分の担当業務もあるので、残業が多くなってしまいます。この状況をいかにして改善していくのか、それが本書のテーマです。
本書で提案されている具体的な方法がとても勉強になりました。その1つは会議にかけるコストを8分の1にするというものでした。それは①会議資料を2分の1に、②会議に参加する人数を2分の1に、③会議時間と開催頻度を2分の1に。そして①×②×③=8分の1というものです(254ページ)。私は「何という斬新なアイデアだ」と驚いてしまいました。
しかし、たとえば「不要な議題を捨てる」ことができれば③は実現できそうです。考えてみると、参加者で議論して意思決定することに議題を絞り込み、そして情報共有や相談は会議以外の個別の機会に、というふうにすれば会議時間・開催頻度は減らせることが多いのではないかと思いました。
それから②の会議資料を2分の1に、は資料をテンプレート化することで実現する、というのが小室さんの提案です。日時、議題、今後の具体的な行動内容、が主な議題となるはずなので、それを記入するテンプレートを用意しておく。それ以外の部分で、あまりに凝った資料づくりは企業にとって非効率を招くという考え方です。もちろん、業種や職場によって議題は異なりますが、会議で主に時間を割くべき事柄に絞り込んで会議を設定するということが重要だと感じました。
それから、②会議に参加する人数ですが、私はアマゾンの創業者ジェフ・ベゾスの「ピザ2枚理論」を思い出します。ピザ2枚分でお腹がいっぱいにならないほどの大人数で会議をするのはムダだという考えです。つまり会議は最大で5~8人程度で行うべし、というものです。ですので、会議参加人数を減らすという小室さんの考えに賛成したいと思いました。
その他にも、「属人化は深刻なリスク」という指摘がありました(187ページ)。特定の誰かに業務が集中したり、誰かでなければある業務が遂行できない状態では、もしその誰かが急病になったり、育児や介護の負担が生じて出勤できない場合に職場の業務がストップしてしまうということです。そうならないためには、業務内容をマニュアル化・フォーマット化しておくこと。そして、ペアになって業務を行っておくなどしてバックアップ体制をつくっておくこと。そうすることでメンバーの力量も上がりますし、マネジャーやメンバーが長期休暇を取得しやすくもなるというメリットが生じます。とても大事なことだと思いました。
もう1つ付け加えると、メンバー同士の心理的安全性が高い職場、メンバーの発言量が比較的均等な職場は生産性が高く(63ページ)、反対に、マネジャーの独演会のような会議が多い職場は生産性が低い(80ページ)という指摘がありました。そして、「マネジャーはメンバーより優秀でなければならない」という思い込みを捨てることが職場の心理的安全性を高めるうえで重要という本書の指摘がとても勉強になりました。
本書は著者の小室淑恵さんが代表をしている㈱ワーク・ライフバランスが1000社以上の企業を対象に実際に提案し、働き方改革の実績をあげてきた実例をもとに書かれています。私としても、まずは長い会議の議題を絞って短縮するところから実現できればいいなと思いました。