スマホ時代を生きる子どもの生活とアクティブ・ラーニング
堀裕嗣 著『アクティブ・ラーニングの条件』
(小学館、2019年)
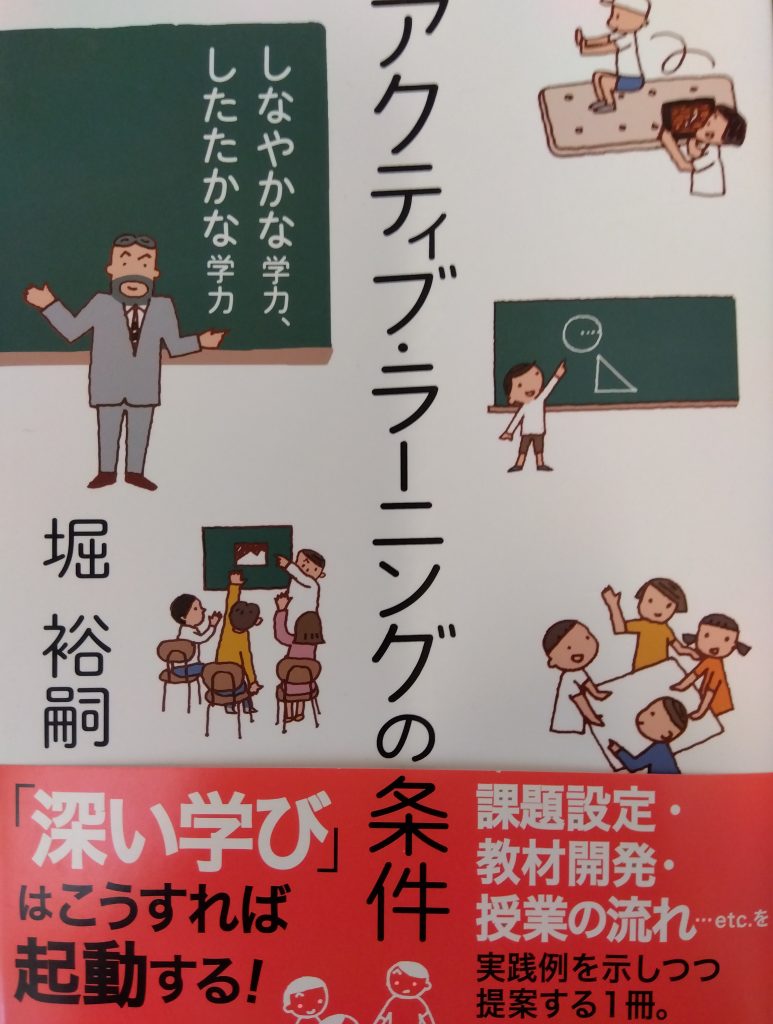
学校の授業風景は、先生が話したり板書したりしたことを生徒が聞いてノートをとるというのが定番のようになってきましたが、グループでの話し合いやプレゼンテーションなどを取り入れたアクティブ・ラーニングを取り入れる動きが広がってきているようです。齋藤孝さんの『新しい学力』など、アクティブ・ラーニングに関連する本を何冊か読んできましたが、今回は本書『アクティブ・ラーニングの条件』を読んでみました。
本書の著者、堀裕嗣(ほり・ひろつぐ)さんは北海道の中学教師で、国語を専門として教鞭をとっておられます。本書を読んで、私が特に勉強になったのは以下の4点です。
1. 出力型授業への転換が必要
本書では1997年という早い時期に、「出力型授業」への転換を提唱した小西正雄さんの『消える授業 残る授業』という本が紹介されています(46ページ)。子どもの表現やアウトプットを重視する授業に転換していく必要を述べた本です。
小西さんは、テレビが子どもたちに提供する情報量の多さ、特に視覚情報の多さに注目して、学校の教室で教師が子どもたちに知識を入力する授業は時代遅れだと指摘しました。子どもに情報を入力する役割として、教師はテレビに勝てない。子どもたちはテレビと教師を比べて、教師の授業をつまらないと感じるだろう、ということです。
そして、今や時代はテレビだけでなく、インターネット、スマホに簡単にアクセスできる時代です。これが「入力型授業」から「出力型授業」の転換を促した結果、子どもの表現やアウトプットを中心とするアクティブ・ラーニングが必要な時代になったのだなと気付きました。
2. 答えのない課題に挑む
堀さんは、従来の一斉授業は、知識を与える「入力型授業」だったとことに加えて、「どこかに最良の答えがあるはずだ」という前提に立っていたことを指摘しています(115ページ)。
これに対してアクティブ・ラーニングは、自分が納得できる最適解をつくる教育だと捉えています。そして、子どもたちが意欲的に取り組んで、最終的な答えは子どもたちの判断に委ねられるものと指摘しています(165ページ)。これは例えば、文芸誌の短歌の入選作品を選ぶ選考委員になったと仮定して、短歌の優劣を議論し判断するといったものです。言われてみれば、現実の世の中では、こうした選考は行われていて、どれが最適解なのかは、本当のところは分からないという面があると気付き、少し驚きました。
3. 5W1Hの中でwhyとhowは特別
問いを発する時、英語の5W1Hを意識するとよいというのは、どこかで聞いたことがあるように思いましたが、本書ではwhyとhowは特別だということが書かれていて、とても勉強になりました(177ページ)。
つまり、何what、いつwhen、どこwhere、誰whoは、たいていの場合は一問一答になり、確認的な質問にとどまります。だから教師はそれを指摘しやすい。説明もしやすい。
これに対して、なぜwhyと、どのようにhowは解釈に差が出やすいので、子どもたちの中からいろいろな意見が出る傾向が強くなります。そうすると、違いを対比したり、詳しく検討したりするプロセスが必要になる。これこそがディスカッションのテーマとしてふさわしい問いになるというわけです。これから質問する時には、こういう違いがあることを意識していくことが大事だと思いました。
4. 「学び」「気づき」「驚き」を記録する
日記というのもアウトプットの重要な手段ですが、堀さんはアクティブ・ラーニングにおいて「ちょっとした気づき」や「些細な驚き」をノートやワークシートに記録させていますか? と問いかけています(193ページ)。記録しなければ、散逸し、忘れてしまいます。これはとてももったいないことだ、と堀さんは強調しています。子どもだけでなく大人も、「ちょっとした気づき」をノートや手帳に記録する習慣の大切さは、ノート術や手帳術の大切さを述べている本でも読んだことがありました。多くの人に知ってほしいことだと思いました。
本書を読んで、現在は授業のあり方が大きく転換している時期なのだと思いました。従来型の一斉授業、知識の入力を重視する授業は完全にはなくならないものの、徐々にアクティブ・ラーニングの比重が高まってきている、その過渡期にあると思いました。


