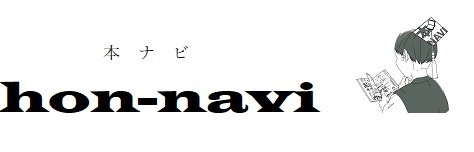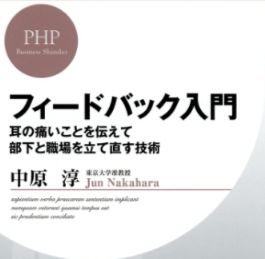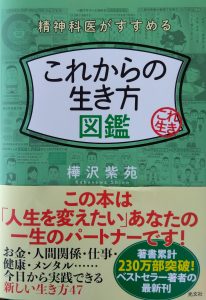ドイツと日本の戦後思想を比較すると見えてくるものがある
仲正昌樹 著『日本とドイツ:2つの戦後思想』
(光文社、2005年)

今年(2025年)は終戦後80年の節目の年にあたります。日本人の多くは戦後生まれで戦争を直接経験していません。しかし、ウクライナや中東の戦争のニュースを見聞きするたびに、戦争の悲惨さが伝わってきて、平和を願ってやまない気持ちになります。
アマゾンのkindle unlimitedというサブスクで読める本のリストのなかに本書『日本とドイツ:2つの戦後思想』を見つけました。出版されたのは2005年なので今から20年前です。この年は戦後60年の年で、日本とドイツの戦後思想を比較する本となっています。昨年(2024年)に日本被団協がノーベル平和賞を受賞して、核のない世界を願う日本初の運動が世界的に認められたということもあり、本書の内容に興味を覚えました。日本とドイツは両国ともに先の大戦の敗戦国なので、共通する部分が多くあるのではないかと思いましたが、読んでみると、両者の違いの部分が浮き彫りとなってきて、とても驚きました。
特に以下の点が重要だと思いましたので、ご紹介します。
広島・長崎とアウシュヴィッツ
先の大戦の悲惨さを伝える場として、日本には広島・長崎があり、ドイツにはポーランド領内のアウシュヴィッツがあります。どちらも反戦・平和運動の象徴的な場所として世界的に知られています。
ところが、違いがあります。アウシュヴィッツはナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺(ホロコースト)の場所ですが、広島・長崎は原爆が投下された場所です。ドイツにとってアウシュヴィッツは加害の場ですが、日本にとって広島・長崎は被害の場です。本書のこの指摘はとても重要だと思いました。
戦争当事国は、お互いに加害と被害を行うことになってしまいます。大戦時の日本もその例外ではありません。ところが、広島・長崎への原爆投下による被害のインパクトはあまりに強烈です。その結果、戦後の日本で行われてきた平和運動や平和教育は、加害よりも被害のほうに目が向きやすかったという本書の指摘は、とても重要だと思いました。
私も以前、広島の平和記念館に行って、展示を見ましたが、あまりに強烈で、戦争の悲惨さが伝わってきたのですが、その悲惨さは被害のほうを中心にしたものだったと感じます。
「ナチズムとの決別」か「戦争放棄」か
ドイツと日本の戦後思想を比較すると、ドイツの場合、「ナチズムとの決別」が主要なテーマとなったのに対して、日本では「戦争放棄」が主要なテーマとなったと本書では指摘されています。ナチスはユダヤ人虐殺に象徴される暴力的な破壊行為を行いました。それは、人間の野蛮性というふうに一般化されて、人間の野蛮性につながるような要素をどのようにして取り除くのかという議論が1つ。もう1つは、ナチスがドイツ国内の市民の身体管理を徹底して秩序化を図ったので、それをどのように防ぐのかという議論。それらはホルクハイマー、アドルノ、ハーバーマスなどのフランクフルト学派と呼ばれる思想家たちの中心テーマとなりました。
日本の場合、日本国憲法第9条の「戦争放棄」を中心とする「護憲平和」主義が政治的左派の重要課題となりました。これに対抗する政治的右派は9条を焦点として改憲を目指し、憲法9条が対立軸となりました。
日本とドイツの違いという意味では、ドイツでは大戦期のナチスとの完全決別が目指されたのに対して、日本では大戦期の天皇制は戦後も象徴天皇制として憲法に温存されたことによって、戦前との完全な決別というよりは「ソフトランディングな体制の転換」が図られたという本書の指摘は「なるほど」と思いました。
戦争責任という難題
戦争責任をどう果たすのかは、いろいろと議論が紛糾するテーマではないかと思います。本書を読んで、日本だけでなくドイツでも、この問題がいろいろと議論されてきたことが分かりました。
「人道に対する罪」という概念が、大戦後の国際軍事裁判で用いられ、ナチス・ドイツの加害行為が裁かれました。ナチスの最高幹部たちは、この「人道に対する罪」で有罪とされました。
ただ、日本の場合、「人道に対する罪」を国家として受け入れたのかどうかが曖昧だと本書で指摘されています。
戦争に直接加担したわけではない、戦後生まれの人々が戦争責任をどこまで負うことが必要なのか。単純な連帯責任という論理だけではうまく捉えることができません。本書では、ドイツでとられている考え方として、「親の遺産を相続する時に、負の遺産(借金)も一緒に相続しなければならない」という論理が紹介されていました。
それともう1つ、国家が被害者に補償を行うことと、個人の内面的な責任は別ということも指摘されていました。
本書は、とかく難解になりがちな哲学・思想を分かりやすくポイントを解説してくれる良書だと思います。西洋、特にドイツの現代思想を学びたい方や、日本とドイツの戦後思想を学びたい方に是非おすすめの1冊です。