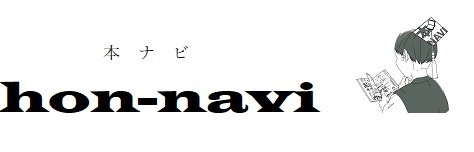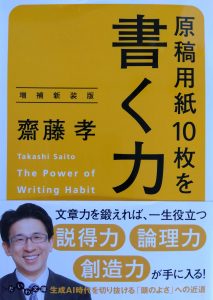スタンフォード大学の行動科学者が力説:習慣化のカギは「小さな達成」と「シャイン」
BJフォッグ 著『習慣超大全』
(ダイヤモンド社、2021年)
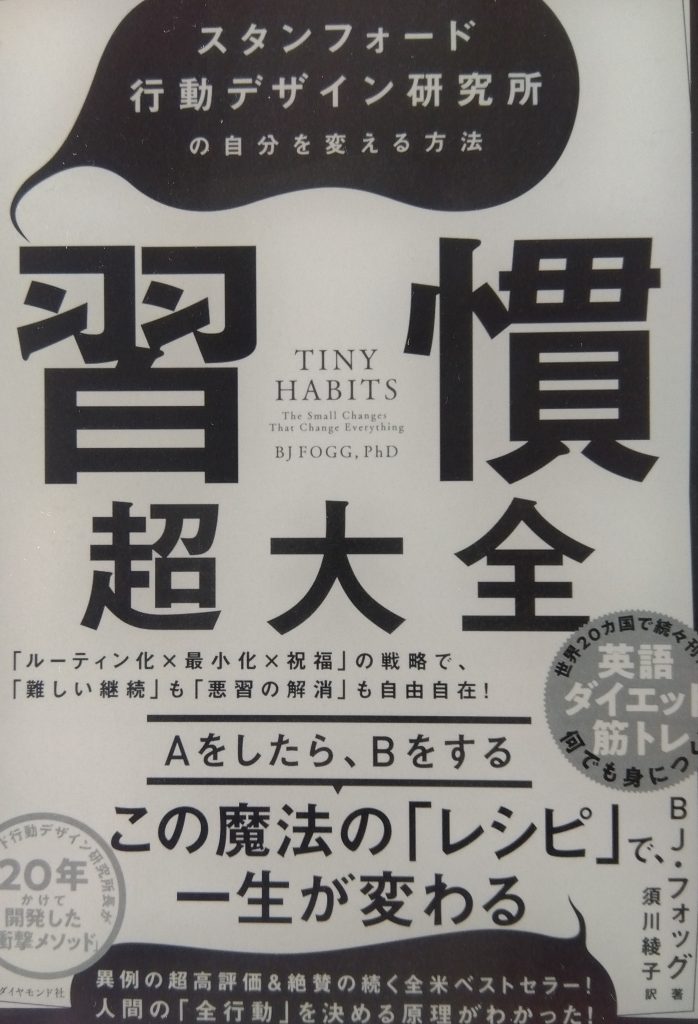
「継続は力なり」と言います。何かを続けるということはとても重要だと思います。私が2年ぐらい前に初めたことで続いているのは、寝る前の日記、散歩などがあります。日記はときどき書くのを忘れる日もありますが、1年のうち360日ぐらいは書いています。散歩は強風の日などは行きませんが週5日ぐらいは歩いています。
最近読んだ本の中では、井上新八さんの『続ける思考』という本がとても面白かったです。この本の参考文献にあがっていたのが今回紹介する『習慣超大全』です。
本書の著者BJ・フォッグさんはスタンフォード大学の教授で行動科学を専門とされています。600ページを超える大著ですが、私が読んで、特に勉強になった箇所を紹介したいと思います。
「今日は素晴らしい日になる」と声に出す
本書の冒頭のところでは、どんな習慣を選ぶかは人それぞれなので、特定の習慣を推奨はしないと述べていましたが、例外として1つだけ、朝、起床とともに「今日は素晴らしい日になる」と声に出して言うことが推奨されています(17ページ)。
これには2つの意味が込められていると思いました。1つ目は、習慣を形成するのは朝が最適だということ。2つ目は、何かをしたら、それを「きっかけ」として何かをすることが習慣化にとって重要だということです。
1つ目の「朝が重要」ということについては、「やる気は朝から夜にかけて低下していく」(243ページ)、「朝の課題をうまくこなせると1日が上向きにスタートし、それによって気分も上向き、その後の仕事や生活において生産性も高まる」(359ページ)とも述べられています。
朝のルーティーンは井上新八さんの『続ける思考』でも、とても重視されています。私も朝の過ごし方をもっと工夫していきたいと思いました。
B=MAP
これは日本語で言うと、「行動=モチベーション×能力×きっかけ」ということです(423ページ)。behavior=motivation×ability×promptの頭文字をとったものす。行動科学者であるフォッグさんが長年の研究で導き出した法則ということで、本書でたびたび説明されています。
この定式のポイントは、ある行動が習慣化しないことを「人間の意思の弱さ」のせいにしていないということではないかと思いました。行動を習慣化するコツは、モチベーション・能力・きっかけの3つを適切に調整すること、というのが本書の全体的な主張です。
モチベーションが高い/低いということだけで、行動を習慣化することは難しいという意味もありそうです。運動習慣を身につけたいという、モチベーションが高い状態であっても、いきなり長距離を走るとか、重いバーベルを上げることはできません。つまり、モチベーションと能力の組み合わせを調整しなければ運動習慣は身につきません。
また、忙しい生活を送っており掃除をする習慣がないという場合、それでも何とか日々の生活は回っているので、掃除をする「きっかけ」がないという意味もあると思います。ところが、友人を部屋に招くことが「きっかけ」になって掃除をし、それ以降、掃除をすることを心がけるようになったという場合のように「きっかけ」も習慣化の重要な要素です。
心地よい感覚(シャイン)
本書では、習慣をつくるには、小さい行動を達成した場合でも、「イエーイ」と声に出したり、ガッツポーズをしたり、家族とハイタッチしたり、といった自分や友人、家族による祝福が大事だと述べられています(310ページ)。この祝福は、心地よい感覚を与えるものです。これまで英語には、この「心地よい感覚」を言い表す言葉がないというフォッグさんの指摘は私にとって意外でした。知りませんでした。フォッグさんは、shine(輝き)という言葉がふさわしいと述べています。本書ではカタカナで「シャイン」と表記されていました。
To Doリストにやるべきことを書き出して、達成したらそれに線を引いて消すということを私はやっています。そういう方はけっこういるのではないでしょうか。この方法は、何かをする「きっかけ」を与えてくれますし、達成して線を引くという行為が、一種の祝福で、「シャイン」を与えてくれると思いました。To Doの内容を小さく分けて、達成したら線を引くという方法を続けていきたいと思いました。