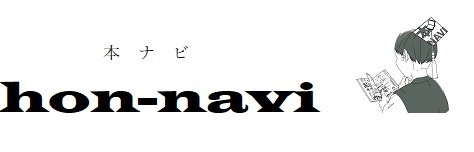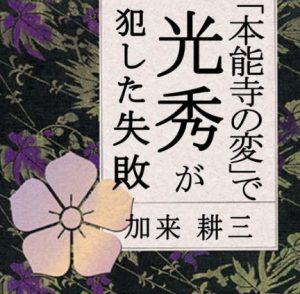角田光代さんの最新小説『方舟を燃やす』はコロナ前と後の世界を見通す
角田光代 著『方舟を燃やす』
(新潮社、2024年)
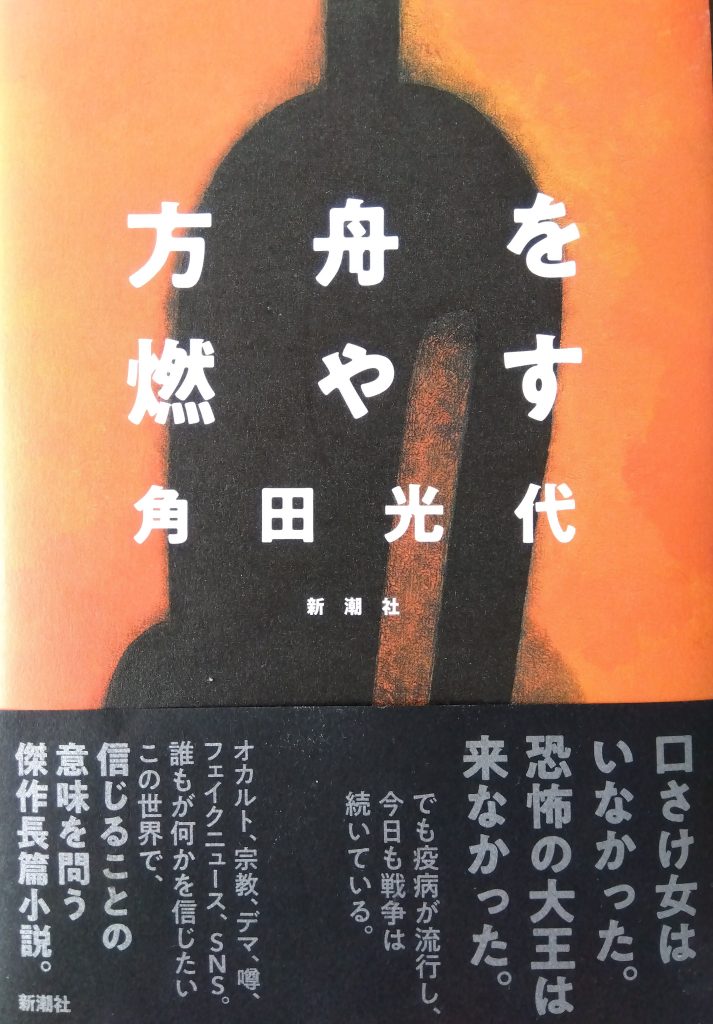
角田光代さんの最新小説『方舟を燃やす』を読みました。以前、角田さんの『対岸の彼女』を読んで、内面描写や人間関係の描き方が本当にリアルだと感じた作家さんです。
ただ、角田さんの本を何冊も読んでいるわけではありません。それは『対岸の彼女』で扱われた「何のために生きるのか」「年を重ねるのか」というテーマが私にはとても重くて、読むのが苦しいとも感じたからだと思います。しかし、家族の薦めもあって、最新作『方舟を燃やす』を読んでみることにしました。
この小説の主人公は柳原飛馬と望月(旧姓、矢部)不三子の2人。年齢は不三子のほうが10歳以上、上です。2人が恋愛するとか、結婚するとかのストーリーではありません。住んでいる場所も全然離れていて、接点がありません。
この2人の1960年代からの生い立ちが別々に描かれていき、小説の終盤で、子ども食堂の運営で接点をもつというストーリーです。2人の周辺の話題や事件として「コックリさん」「口裂け女」「ノストラダムスの大予言」「2000年問題」、阪神淡路大震災、カルト教団によるテロ事件などが触れられます。このような事件やブームを私も体験してきました。「人が何かを信じるとはどういうことか」という著者の角田さんの問いかけが伝わってくるような気がしました。
ほかにも、無線による通信、雑誌の文通コーナーなども触れられています。これらは「人とつながりたい」という根源的な欲求をもっていることの表れであるように思います。現代ではインターネットやスマホの開発によって、かなりスムーズに「人とつながる」ことが実現できる世の中に変化しています。
この小説は、時代状況と2人の主人公の人生が重ね合わせられるかたちで、静かに進行していったように感じました。『対岸の彼女』のほうが、激しい展開があったように思いました。
不三子という女性は結婚した直後から添加物の多い食事を避ける自然食にのめり込んで行きます。そのきっかけは公民館で聞いた、自然食の指導者の話に感銘を受けたことです。自分と娘、息子には玄米食を貫きました。夫はそれに強く反発し、夫の食事は別のものを作ります。そして、娘、息子が学校に入学すると、学校に直談判し、給食を食べさせず、玄米中心の弁当をもたせます。さらには、予防接種の必要性に疑問をもち、自分の娘、息子には予防接種を受けさせませんでした。
ここまで徹底することは、日本の社会状況では簡単ではないと思います。人と同じ、横並びというのが好まれる傾向にあると思うからです。
そして、不三子の人生は、世間との折り合いがあまりうまくいかない人生として描かれていました。不三子は、ある時期から娘の反抗を受け、娘は家を出ていって音信不通になってしまいました。
そして、子ども食堂で2人が接点をもち、直後にコロナのパンデミックが発生します。この時、予防接種を疑問視してきた不三子の経験が、もう一度繰り返されます。コロナ・ウィルスの予防接種は受けるべきなのかどうか? みんなが接種しているから接種するのか? 無料だから? 副反応の問題は数年、数十年の単位ではどうなのか?
このようなストーリーの終盤の展開が私には本当に面白かったです。それは不三子と飛馬の人生の終盤の出来事で、私がこれから経験する老後のことを想像することになりました。
不三子の人生は、あまりいいことばかりではなかったように思いましたが、それでも人生終盤に、それまでの疑問が解けるような、そして、少しは報われるような出来事がありました。その1つは、自然食への不三子こだわりが、子ども食堂の提供するベジタリアン料理に生かされたことです。実は不三子は時代の最先端を不器用に走った人物として描かれたのかもしれないと思いました。
角田さんはいろいろな文学賞を受賞されていますし、小説の一部は高校の国語の教科書にも掲載されているようです。角田さんの他の本も読んでみたいと思いました。